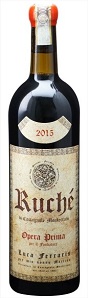オリオル・ロッセール ロゼ・ブリュット

生産産者:オリオル・ロッセール(スペイン、ペネデス)
使用品種:ガルナッチャ60%、ピノ・ノワール40%
オリオル・ロッセールが造るフレッシュでフルーティーなロゼ・スパークリングワイン。手作業の動瓶作業が生み出すキメ細やかな泡、甘酸っぱいイチゴを思わせるチャーミングな果実味が口の中いっぱいに広がります。自家葡萄園でオーガニック栽培されたガルナッチャとピノ・ノワールで造られています。¥1,705(税込)
プラン・ド・デュー キュヴェ・エゴイスト

「エゴイスト!?」・・現当主ベルナールが学生の頃から好きで好きでたまらず、今も娘にも手伝わせない本当に「エゴイスト」な畑のブドウのみでこのワインは造られます。先代の父エドモンが、いとこの所有していた当時まだ森だった土地を借り受け、その後いとこが亡くなって貰い受け、1971年にまだ学生だったベルナールが父エドモンと共に葡萄を植え、初めて任されたプラン・ド・デューの丘にある1haほどの思い出の畑です。
90%フリーランジュース、10%プレスジュースをブレンドした後、タンクでマロラクティック発酵。熟成は、コンクリートタンクで12ヶ月行います。清澄はせず、軽くフィルターを通します。濃い紫色。プラムを思わせるアロマ、バランスがよくしっかりとした骨格があります。
テラム コート・デュ・ローヌ ルージュ

現当主のジュリー氏の夫ニコラ・リシャルム氏の父はコルシカ島でビオディナミ栽培のワインを造ってきた経験もあり、1997年から20年以上にわたりその経験を活かしビオディナミ栽培を実践し、収穫の少ないクローン種に切り替え、自分たちの土地に合う採用する研究を重ねてきました。
「大地」を意味する「テラム」と名付けられたこのワインは、コート・デュ・ローヌの真骨頂を味わえる力強い1本です。生産者はこのワインに「大地のように静かでどっしりとしたさま」をイメージしていることからこの名がつけられました。醸造はステンレスタンクにて、3週間かけて温度調整をしながら発酵。土壌は粘土とシリスです。赤い果実の味わいが特徴的で、透き通るようなミネラルと繊細な酸を感じとれます。肥沃な土壌なので、厚みもしっかり出ています。
ローラン・ラ・ギャルド

ジロンド河を挟んでサンジュリアンの対岸に位置するサン・スーラン・ド・キュルサックにあるシャトー・ローラン・ラ・ギャルド。なだらかな傾斜が続くブライの土地の中でも小高い丘の上にある約29ヘクタールの一枚畑を持ち、日当たりと水捌けのよい傾斜、ジロンドから吹き抜ける風などテロワールの恩恵を受けています。ヴィニュロンであるブルーノ・マルタン氏は、父の代からの自然農法を受け継ぎ、化学除草剤などは使うことはしません。現在はビオロジックを導入し、認定も受けています。
写真 左のプレスティージは、ブライの風土とマルタン氏のワイン造りの根底が良く表れているキュヴェで、低温マセラシオン、天然酵母による 醗酵、ソフトプレスを行い、バリック(新樽1/3、1年樽1/3、2年樽1/3)にて熟成しています。はっきりと力強い果実の濃縮感、チョコレートやカカオ、ペッパーや香木のスパイシーさや土の香り、細やかさのあるタンニン、シルキーな舌触りの飲み口は優しくも深みとボリューム感に富んだブライでも指折りのワインです。
ルケ “オペラ・プリマ”
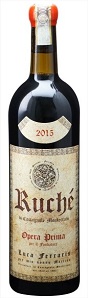
「まったく新しい手法で造られた、高品質なルケ」という意味を込めて「オペラ・プリマ(第1作、最高作品)」という名前を付けています。
現当主ルカ・フェラリスが、創業者である祖父マルティーノに捧げたワインです。
造るのが難しいので毎年造るわけではなく、'13、'14VTは造っていません。ルケ種にはピノ・ノワール種との類似性があると感じたルカは、偉大なブルゴーニュに匹敵するようなルケのワインを造ろうと考え、まずは最高の葡萄が出来る畑を選ぶことから始めました。このオペラ・プリマは「ブリッコ デッラ ジョイア」と呼ばれる単一畑の葡萄を使っています。
アスティ側の南向きの斜面で、標高は285m。土壌はトゥーフォと呼ばれる火山灰が堆積して固まった凝灰岩で、樹勢が強くなりません。非常に日当たりが良いため、葡萄はしっかりと色づき、糖度の高い、粒が小さく凝縮されたものになります。畑を厳しく管理、グリーンハーベストを行い、収穫量を半分まで落とします。機械が入ることの出来ない急斜面のため、収穫は手摘みで行います。葡萄は厳しく選別し、温度管理したロータリーファーメンターで発酵させ、35~45日間醸しを行います。ステンレスタンク(ロータリーファーメンター)でマロラクティック発酵させます。品種の持つ個性を隠してしまわないよう、500Lのフレンチオークのトノー(新樽40%)で24~32ヶ月('15VTは18ヶ月)熟成させます。さらに12ヶ月瓶熟してからリリースします。
バックラベルにはボトリングナンバーを印刷しています。ラベルデザインは、ワインがブルゴーニュスタイルであることを意味しています。「2015年は私の人生で一番のオペラ・プリマができた」とルカは話していました。
【純米吟醸】三十六人衆

鳥海山、日本三大急流の最上川、日本海、ササニシキで有名な庄内平野を眼下に望み、綺麗な空気、清冽な水など日本酒醸造にはまたとない好環境好条件の中で三十六人衆が造られています。特定名称酒は全て蓋麹製法で行なっています。 蓋麹製法は麹の造り方の一つですが、最も手間がかかる造り方で通常は鑑評会用の大吟醸など特殊な高級酒以外は採用しない方法です。かつて、酒田の豪商として自治的に町政を運営し、海上の警備においては町兵を率いて商船で奮戦したほどの自治組織″三十六人衆″が酒名の由来です。
【吟醸】東力士

嘉永2年(1849)創業。2代目当主が無類の相撲好きであったことから酒名も「東力士」と名付けたといいます。那 須岳より湧き出ずる清流那珂川の伏流水を仕込み水とし、良質の原料米と共に恵まれた自然環境の中で丹精込めた酒造りを行っております。近年洞窟貯蔵を試み、35年に及ぶ貯蔵・熟成の経験と実績を持つ国内屈指の長期熟成酒造りの先駆者蔵元として現在も新たなる日本酒の味わいの創造に挑戦しています。
【吟醸酒】浜千鳥

「浜千鳥」の由来は、国立公園に指定されている風光明媚な陸中海岸の浜辺に群れなす千鳥をイメージし、名付けられました。岩手県の豊かな自然に育まれ、さらりとした口当たり、味わい深く後切れが良いのが特徴です。陸中海岸で獲れた新鮮な海の幸、北上山地で採れた山の幸によく似合うお酒に仕上がっています。吟醸酒はフルーティーな香りを漂わせ繊細な中に深みを醸し、純米酒は穏やかな味わい。本醸造は燗でも冷でも、さらりとした飲みやすさがどのようなお料理にもマッチすることでしょう。
【純米吟醸】一好

このお酒は栃木県・那須烏山にある蔵元・東力士の現社長(六代目)との偶然の出会いから生まれた、当店のオリジナル清酒です。中身は県産の酒造好 適米、精米は60%。穏やかな果実香とふっくらとしたまろやかな旨みを 持つ特別純米酒です。
【純米酒】二輪草

「板橋区の酒」を造ろうと板橋区商工課と区内酒販組合の協議により誕生した純米酒「いたばし二輪草」。名前の由来は清楚で親しみのある区の花「ニリンソウ」にあやかって命名されました。このお酒は板橋区には江戸時代、加賀100万石“前田家”の下屋敷があったことから、歴史的にも交流のある石川県金沢市の)福光屋にお願いしました。軽快でキレの良い辛口でありながら、米の旨味が広がる純米酒です。